.avif)
切り絵アニメーションは、100年以上にわたり物語を映像で表現する方法として使われてきました。初期にはロッテ・ライニガーの影絵映画のような作品があり、最近では『サウスパーク』の初期に作られた試作のエピソードにも使われています。紙やイラストを切り抜いて動かす手作りのやり方と、実用的な制作方法を組み合わせたスタイルは、今も多くの映像作品で生き続けています。2025年の今も、その独特の見た目と作業のしやすさにより、クリエイターやブランドによって、さまざまなプロジェクトで活用されています。
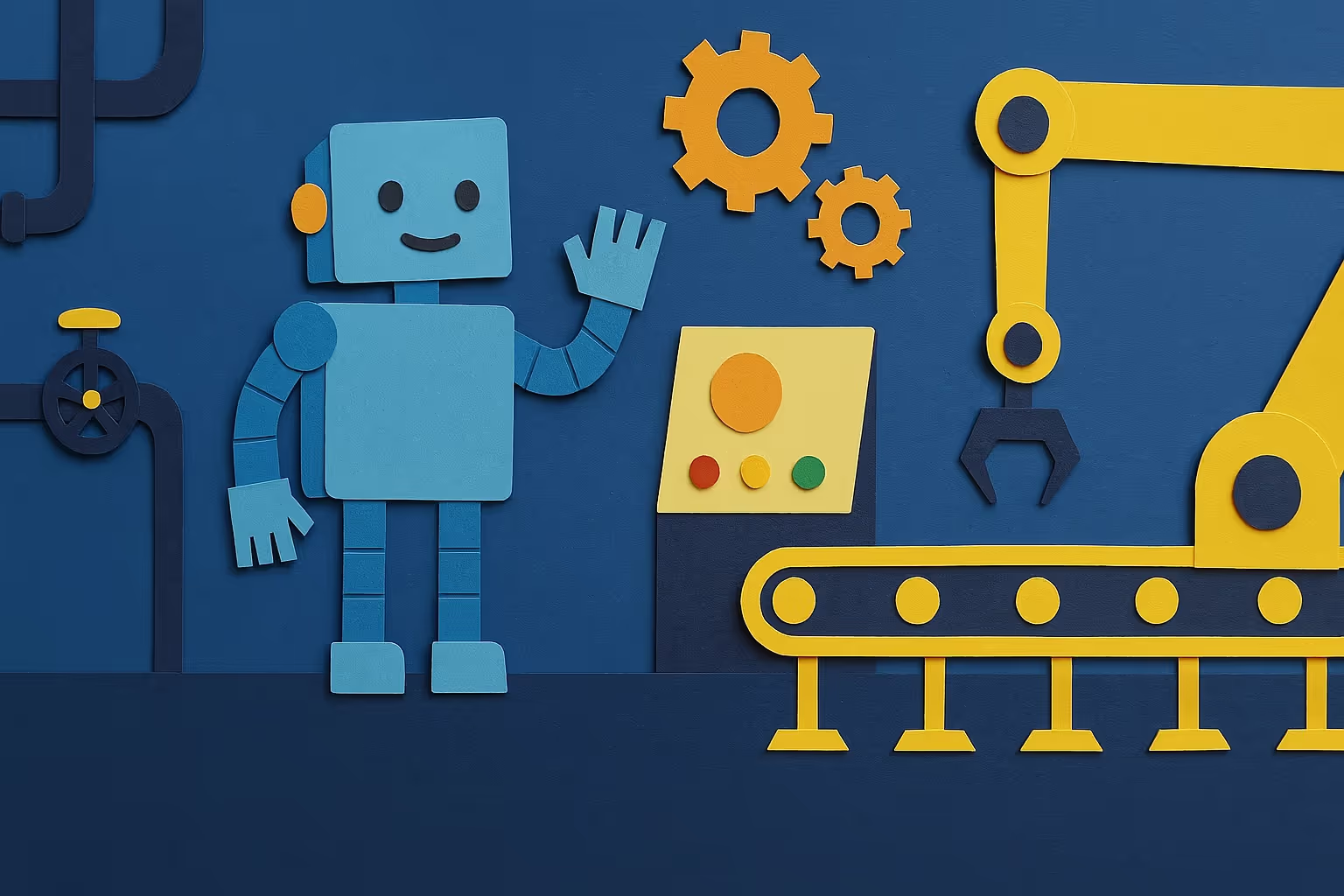
切り絵アニメーションは、ロッテ・ライニガーなど、はじめにこの技法に取り組んだ人たちによる100年以上前の影絵映画から始まり、いまでは紙などの物理素材とデジタル技術を組み合わせたハイブリッド制作へと進化してきました。2025年の現在、『ペッパピッグ』のようなテレビ番組、Kurzgesagtのようなネットチャンネル、SNSの短尺動画などで活躍しています。手作り感のある見た目、低コスト、短い動画への適応力が魅力で、制作の速さ、素材の使い回し、小規模チームで制作できることが強みです。一方で、動きの自由度や複雑なアクションの表現には限界があります。近年の人気復活は、自然で飾らない映像への需要、手頃な制作ツール、ハイブリッド技法の普及によるものです。今後はAI支援やVR実験、デジタルと物理を融合した持続可能な手法が広がり、実用性と創造性の両面で可能性を広げていくでしょう。
ドイツのアニメーター、ロッテ・ライニガーは、1926年の長編作品『アッヘンデ王子の冒険』で切り絵アニメーションを広く世に知らしめました。これは影絵をヒントに、精巧なシルエット人形を使った手法でした。その後、この技法は進化を続け、1970年代にはテリー・ギリアムが『モンティ・パイソン・フライング・サーカス』でコラージュ風の切り絵を使ったシュールなコメディ表現に応用しました。
現在では、コンピューターの登場によって制作方法が大きく変わりました。作業のスピードが上がり、合成もよりきれいに行えるようになったほか、紙やイラストなど手作りの素材とデジタルのリギングを組み合わせたハイブリッドな表現も可能になっています。
2025年現在、手作りの温かみや少しラフな見た目のアニメーションが人気を集めています。これは、精密な3Dやベクターアートとは違う魅力があるからです。切り絵アニメーションは、こうした雰囲気を手軽に出せるうえ、制作コストも抑えることができます。さらに作り方がシンプルなので、TikTokやInstagram、YouTubeなどの短い動画にもぴったりです。そのため、企業の広告から個人の作品まで、幅広く活用されています。
切り絵アニメーションは、平面的な手作りのキャラクターでも複雑な物語を表現できることを示し、映画の初期の歴史に大きな影響を与えました。さまざまなアーティストやイノベーターによって発展し、低コストで作れるうえ、独特の見た目が特徴の技法となりました。そしてこの手法は後のストップモーションにも影響を与え、アニメーションをひとつの芸術として確立するきっかけになりました。
アルゼンチンでは、キリーノ・クリスティアーニが切り絵の手法を使って『ブエノスアイレス州での介入』という初期の短編アニメを制作しました(残念ながら作品自体は現存していません)。彼の政治風刺アニメは、セルアニメが普及するずっと前に南米のアニメーションの土台を築いた、重要な功績です。
ライニガーの影絵アニメーションは、技術的にも芸術的にも非常に重要な作品として今も評価されています。関節でつながれた切り絵の人形は驚くほど滑らかに動き、多くのアニメーターに影響を与えました。
1960年代後半から70年代にかけて、ギリアムは雑誌の切り抜きや奇抜な組み合わせを用い、切り絵アニメーションをシュールな風刺表現へと発展させました。彼の作品は、この手法がコメディや実験的表現にも向いていることを示しました。
セルアニメが主流になる前、日本のスタジオでは紙の切り絵を使って効率的に物語を描いていました。こうした初期の試みは、後のアニメのテンポや画面構成の技術にも影響を与えたと考えられています。
切り絵アニメーションは、その作り方や使う素材など、さまざまな点で他のアニメーション手法とは異なります。
昔ながらの切り絵アニメーションでは、キャラクターや小道具を1コマずつ動かしてそのたびに写真に撮ります。動かす部分にはピンや留め金、簡単な関節を使用して動きを可能にします。細かい作業ですが、セルアニメのように毎回描き直す必要はありません。同じパーツを何度も使えるため、動きはやや制限されますが、作業時間や予算を抑えられる可能性があります。これは作品の規模や制作の進め方によっても変わります。
物理的な切り絵アニメーションでは、紙やボール紙、写真、布などを使います。デジタルの切り絵アニメーションでは、Adobe Animate、After Effects、Toon Boom Harmonyといったソフトで同じ表現を再現します。最近では、紙などで作った実物の素材をスキャンしてデジタル上で動かすなど、両方を組み合わせたハイブリッドな制作も増えています。
切り絵アニメーションは、平らな絵や形を重ねたような見た目が特徴です。1コマずつ動かすため、動きは少し制限があったり、ぎこちなく見えることもあります。また、紙や印刷物を使うことでできる独特の質感が、このアニメーションの雰囲気をつくっています。
切り絵アニメーションと3Dアニメーションは、制作方法も見た目も大きく異なります。物理的な切り絵アニメでは、素材を手作業で作り、1コマずつ撮影します。デジタルの切り絵アニメでも、細かい準備やコマごとに動かす作業が必要です。一方、3Dアニメーションは仮想空間で作ったモデルに動きを付けるため、複雑な動きや視点の移動が滑らかに表現できます。3Dはリアルで動きのある表現が得意ですが、切り絵アニメーションならではの手作り感や質感は、3Dではスタイライズされたレンダリングでしか再現できません。
切り絵アニメーションを作るにはいくつかの工程があり、その進め方は手法によって少しずつ異なります。
まずキャラクターや小道具をデザインし、切り抜いてから動かせるように関節を付けます。次に背景を作り、セットを組み立てます。カメラは真上または固定の角度に設置し、ちらつきを防ぐために光を均一で安定させることが大切です。
After Effectsでは、パペットピンツールを使って関節があるような動きを再現できます。Adobe Character Animatorなら、切り絵風のキャラクターを使ってリアルタイムに動きをキャプチャできます。Toon Boom Harmonyは、切り絵キャラクター向けの高度なリギング機能を備えています。
近年の多くの作品では、手作りの素材を撮影し、それをデジタルで動かしています。中には、3Dプリントしたパーツをストップモーション用の仕掛けに組み込み、立体感と切り絵の雰囲気を組み合わせるスタジオもあります。
Talking Headsの「And She Was」のようなミュージックビデオや、現代のTikTokアニメーションは、切り絵アニメーションが現代でも強い表現力を持ち、幅広いコンテンツで活用できることを示しています。切り絵アニメーションは、時代やプラットフォームが変わっても、その独特の魅力は失われません。
『サウスパーク』は当初、実際の紙の切り絵を使って制作され、その後、手作りの質感を再現できるソフトに移行しました。独特の見た目はブランドの象徴となり、現代のテレビアニメの特徴のひとつとなっています。一方、『ペッパピッグ』などの作品では、デジタルツールを使って切り絵アニメーションの手法が活かされています。
コラージュ技法と不条理なストーリーテリングを組み合わせた、シュールな映像ユーモアの代表作です。多くのアニメーターに影響を与え、今も実験的なモーショングラフィックスの制作に刺激を与え続けています。
科学や技術などの複雑なテーマを、視覚的にわかりやすく解説する人気のYouTubeチャンネルです。動画にはデジタルの切り絵アニメーション技法が使われており、映像の見やすさや内容にうまくマッチしています。
世界のアニメーション市場の大半はCGですが、切り絵アニメーションは広告、教育、インディーズ映画などで注目を集めています。制作コストを抑えられる可能性があり、過剰な高品質のデジタル映像に疲れた視聴者にとっては印象的なスタイルです。ハイブリッド作品やデジタル切り絵アニメーションも広く知られており、特に人気のある用途としては、2DモデルのVチューバー用リギングが挙げられます。

2025年、切り絵アニメーションが再び注目されているのは、文化的な理由と実用的な理由が重なっているためです。手作り感のある表現が好まれるようになったことに加え、短くループする動画形式との相性が良いため、SNS向けコンテンツにも向いています。また、手頃なツールや素材が増えたことで、個人のクリエイターでも始めやすくなっています。さらに、スタジオや教育現場でも、芸術的価値やさまざまなプロジェクトへの応用力が評価され、この技法が広く使われています。
切り絵アニメーションは、手作りの質感によって感情に訴える力があります。ブランドストーリーの表現や解説動画、SNSキャンペーンなどに適しており、同じ素材を使い回したり加工したりできるため、複数のキャンペーンでコストを抑えて活用することも可能です。
今後は、AIを活用した制作や、他のアニメーション手法とのハイブリッド化が進むと考えられます。物語形式のVRコンテンツのようなインタラクティブ体験に応用される可能性もありますが、まだニッチで、他のアニメーションほど普及しているわけではありません。また、デジタルツールを使うことで素材の無駄を減らしつつ、手作り感のある見た目を維持できるため、持続可能性も注目されています。テリー・ギリアムの言葉を借りれば:
「僕にとってアニメーションの本質は、物語を伝えたり、ジョークを見せたり、アイデアを表現することです。技法自体はあまり重要ではありません。使えるものを使えばいい。それが切り絵アニメーションを使う理由です。僕にとっては、これが最も手軽にできるアニメーションの方法だからです。」
2025年の今、この言葉は以前にも増して実感できます。配信サービスの作品でも、教室での教材でも、ブランドのSNSでも、切り絵アニメーションは「優れた物語を生み出すのは技法ではなく創造力そのものである」ということを示しています。