
スクイグルビジョンは、線を常に揺らして動いているように見せることで、低コストで映像を作れる画期的な手法として、1990年代のテレビアニメに大きな変化をもたらしました。最初に登場したのは、グランジ・カルヴリーによるイギリスの子ども向けアニメ『ルーバードとカタード』で、その後トム・スナイダーが復活させました。この特許技術は、『ドクター・カッツ:プロフェッショナル・セラピスト』のような隠れた名作を生み出し、H・ジョン・ベンジャミンをはじめとするコメディアンたちのキャリアを切り開きました。
スクイグルビジョンとは、キャラクターや物の輪郭がずっとわずかに震えるように、揺れ続けるアニメーションの手法です。いくつかの微妙に違う絵を切り替えて見せることで、生き生きとした動きを感じさせます。たとえ完全に静止した場面でも、線が常に揺れているため、視聴者の目には動きがあるように映るのです。この効果はデジタルでも再現でき、手描きアニメのラフな味わいを残しつつ、コマごとに一枚ずつ描く方法よりも安く効率的に作れるのが特徴です。

スクイグルビジョンは、1970年代のアニメ『ルーバーブとカスタード』で初めて使われましたが、1990年代初めに トム・スナイダー(Tom Snyder Productionsの創設者)によって復活しました。彼はアニメーターであると同時に教育者でもあり、常にメディアを低コストかつ工夫して活用する方法を模索していました。そのスクイグルビジョンが本格的に脚光を浴びたのは、1995年に始まった『ドクター・カッツ:プロフェッショナル・セラピスト』でした。当時、アニメ制作費の高さがテレビ業界の大きな課題となっていましたが、スクイグルビジョンは費用を大幅に抑えられる手法として注目され、制作を効率化できるコンピュータ技術への関心の高まりとも重なりました。
スクイグルビジョンは、シンプルなループで成り立っています。わずかに異なる同じ絵を5枚を作り、この順番を高速で切り替える「フリック」という方法で見せます。各フレームで線が少しずつ揺れることで、独特のブレたような動きが生まれます。トム・スナイダーのチームは、この作業をDOS上の Autodesk Animator というソフトで行いました。ソフトの機能は限られていましたが、それでも十分にスクイグルビジョン特有の揺れを表現できました。
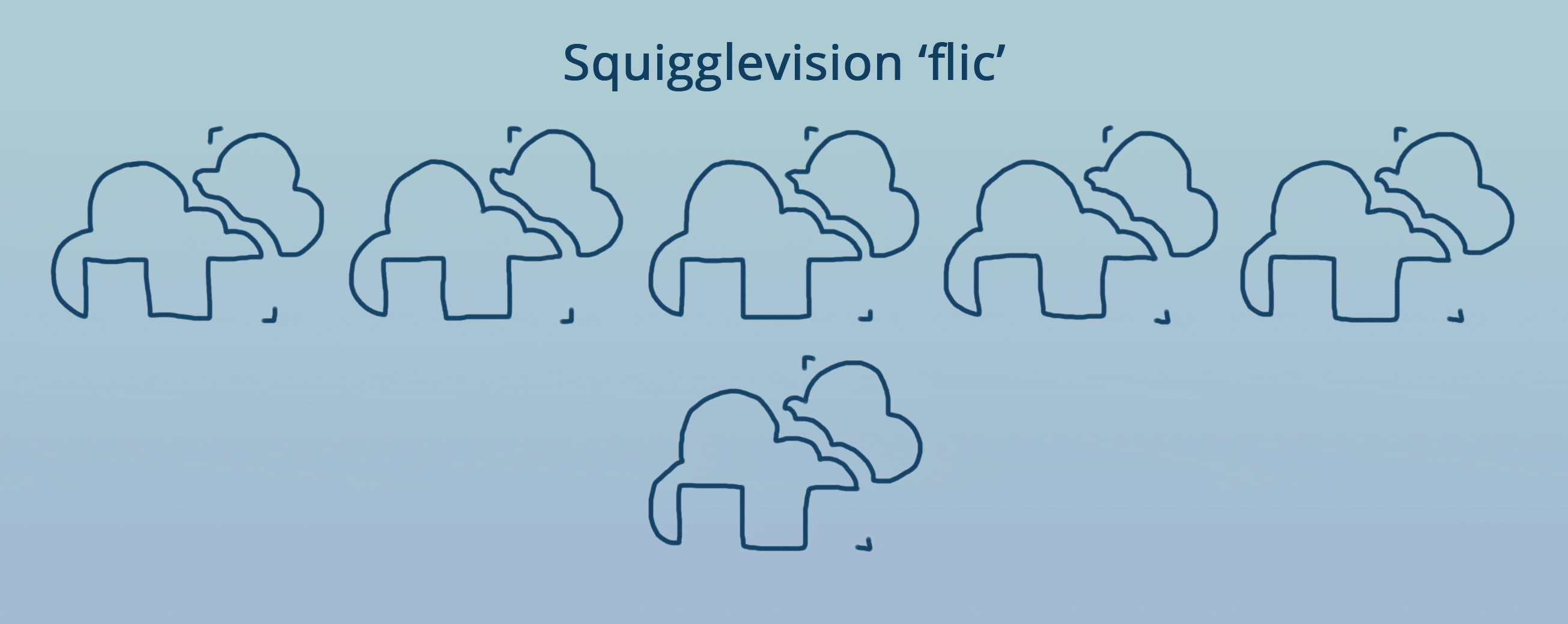
フリックができあがると、Avid Technologyの編集システムでつなぎ合わせ、映像として完成させます。スクイグルビジョンは、トム・スナイダーが「動きの節約」と呼んだ考え方に戻づいてます。キャラクターを大きく動かさなくても、線が揺れているだけで生き生きと見えるのです。だからこそ、複雑で手間のかかるアニメーションを作る必要がなくなり、制作をスピーディーかつ低コストで進めることができました。
20世紀の終わり頃、アニメ制作にはますますお金がかかるようになっていました。ビバリーボーイ・プロダクションズの記事によると、2018年のCGアニメ映画の制作費は1本あたり平均で約3,370万ドル、ストップモーション作品は完成した映像1分ごとに約5万ドルかかっていたそうです。さらに、手描きのテレビアニメは大人数のスタッフと膨大な時間が必要で、資金力のあるスタジオでしか続けられませんでした。
トム・スナイダーが出した答えは、アニメをとことん効率化し、コストを抑えるためにスクイグルビジョンを生み出すことでした。インタビューで彼はこう語っています。「スクイグルを使えば、アメリカのどんな競合よりも千分の一のコストで作れるんです。しかも、ほとんど欠点がありません。」さらに彼は、リビングでの何気ない会話シーンでも、派手なヘリコプターのシーンでも、制作にかかる手間やコストはほとんど変わらないと説明しました。この手法のおかげで、シーンの種類に関わらず同じ労力で映像を作ることができたのです。
スクイグルビジョンが初めて大きな注目を集めたのは、1995年から2002年までコメディ・セントラルで放送された『ドクター・カッツ:プロフェッショナル・セラピスト』です。物語はセラピストのカッツ医師が、ソロ芸人たちを診察するという内容で、診察の場で芸人たちが自分のネタを実際に演じるスタイルでした。この形式により、アニメとライブのコメディが組み合わさった独特の演出が生まれ、H・ジョン・ベンジャミンやローラ・シルバーマンといった芸人を世に送り出しました。作品はその斬新さでピーボディ賞も受賞しています。また、この作品では「レトロスクリプティング」という手法が使われました。これは台本を細かく決めず、会話を即興で進める方法です。スクイグルビジョンの線の揺れによって、こうした自由な演出でもスムーズに制作できたのが大きな特徴です。
スクイグルビジョンは大人向けコメディだけで使われたわけではありません。1997年、スナイダーのスタジオは『サイエンス・コート』という教育番組を制作しました。この番組では、科学の概念を法廷ドラマに置き換えて紹介しています。ABCの子ども向け枠「キッズ・ワン・サタデー・モーニング」で放送され、独特の揺れるアニメーションを子どもたちにも届けました。判事のストーン(声:ポーラ・パウンドストーン)やパーソンズ教授(声:H・ジョン・ベンジャミン)といったキャラクターたちが、ユーモアを交えながら科学をわかりやすく伝え、スクイグルビジョンの多様な表現力を示しました。
もうひとつの代表作が、1999年に始まった『ホーム・ムービーズ』です。第1シーズンではスクイグルビジョンが使われましたが、第2シーズン以降はフラッシュ・アニメーションに切り替えられました。この変更の理由は、揺れる線の表現が視聴者や批評家から批判を受けたことと、複雑な動きを描くのが難しかったからでした。
スクイグルビジョンは制作費を大幅に抑えることで、小さなスタジオでも作品を作れるようにしました。従来の高額なアニメ制作費では実現できなかった企画にも挑戦できる環境を生んだのです。このように「誰でもアニメを作れる仕組み」が生まれたことで、その後のアニメ制作やデジタル制作の方法にも影響を与えました。
スクイグルビジョンは特にコメディとの相性が良い手法でした。線がゆるく揺れるアニメーションは、アドリブにも自然に合い、新しいタイプのアニメのコメディ番組を生み出すきっかけになりました。台本に頼らず、キャラクター同士のやり取りを自由に演じる「レトロスクリプティング」という手法も好評で、『リック・アンド・モーティ』などの現代作品にも応用されています。
現在(2022年時点)では、アニメーション市場の約85%をコンピューターグラフィックス(CG)が占めています。その中でスクイグルビジョンは、テレビアニメにデジタル技術を取り入れた初期の試みのひとつでした。手描きの絵とデジタル編集を組み合わせたこの手法は、後に業界の標準となる制作の流れを形づくるきっかけとなりました。
スクイグルビジョンは1990年代に注目を集め、新しいデジタルアニメの流れを作りました。線が揺れる独特の表現で『ドクター・カッツ』や『ホーム・ムービーズ』に個性を与えましたが、やがて観客はより滑らかな映像を求めるようになります。その結果、スタジオは複雑な動きや演出ができる新しい技術を取り入れ始めました。2000年代初めには、安く柔軟に作れるフラッシュアニメが登場し、スクイグルビジョンから生まれた作品もこの手法へ移っていきました。スナイダーの発明は終わりではなく、次の時代へつなぐ重要な一歩だったのです。それでもスクイグルビジョンは消えてはいません。今もインディーズのアニメ作家や実験的な映画制作者が、懐かしさを出したり、あえて手描き感を強調したりするために使い続けています。
スクイグルビジョンは現在、一般的なテレビアニメではあまり使われていませんが、その独特な「線が揺れる表現」は今でも作品に影響を与えています。アニメーターはアフターエフェクトやBlenderといったソフトを使い、この揺れる線の雰囲気を再現しています。特にフリーのアーティストたちは、90年代を思い出させる演出として取り入れています。ライティング・アンド・デザインの動画では、Blenderのような3Dソフトでスクイグルビジョンやその応用を再現する方法が紹介されています。
多くの現代的なアニメ表現では、あえて線をゆがませたり不完全さを残したりすることで、温かみや個性を出しています。スクイグルビジョンはその元祖ともいえる存在で、「ラフさも表現の力になる」ことを示しました。SNS向けの短い動画や、Vlog風のアニメーションなどでも、スクイグルビジョンに影響を受けた手法がよく使われています。特にユーモアを強調したいときや、手作りっぽい雰囲気を出したいとき、感情をストレートに伝えたいときに使われることが多いです。低コストで一目でユニークな表現は今も観客を魅了し、昔の技法であっても新しい形として取り入れれば、十分に価値を持つことを証明しています。
スクイグルビジョンは複雑な映像表現ができなかったため、作り手はセリフのやり取りや会話の間合い、キャラクターの面白さに集中しました。つまり「限られた条件の中だからこそ、新しい工夫や面白さが生まれる」ということを示しています。そして同時に、効率を重視しすぎず、作品としての芸術性とのバランスを取ることの大切さも教えてくれています。
スクイグルビジョンを見てわかるように、新しい映像表現は人によって好みが分かれるということです。揺れる線を見づらいと感じる人もいれば、その独特さを作品の魅力として楽しむ人もいます。こうして観客の年齢や文化によって受け止め方が変わることを知ると、新しい表現に挑戦する意味がよくわかります。
スクイグルビジョンは斬新な手法で革命的でしたが、その後ほかのアニメスタイルに移行したことから、革命も進化していく必要があることがわかります。現代のアニメーターは、この例から学び、新しい技術を取り入れつつ、観客の期待に合う制作の流れを整えることが大切だと言えます。